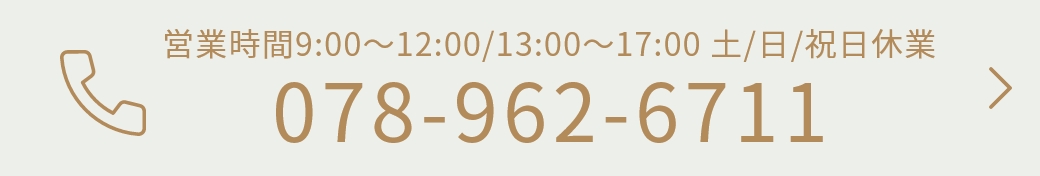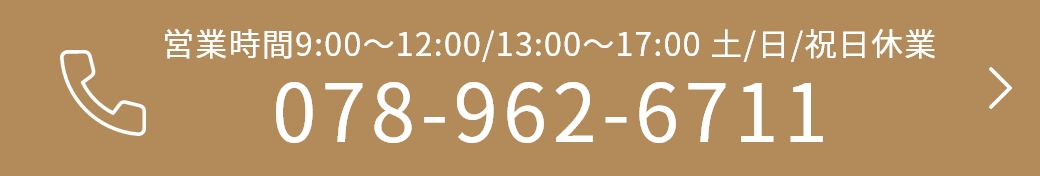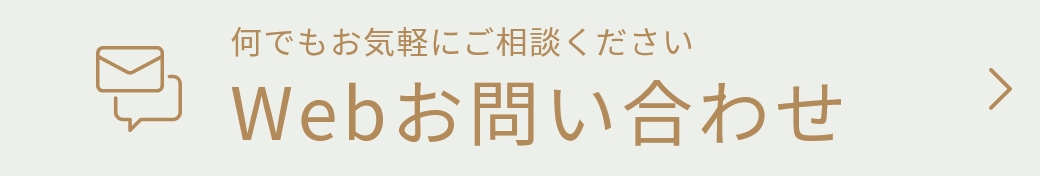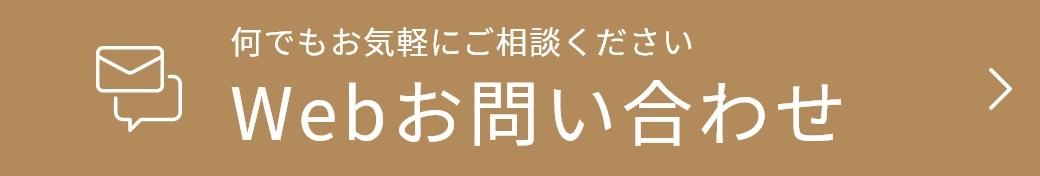遺産分割協議書とは?具体的な作成方法と記載例を解説
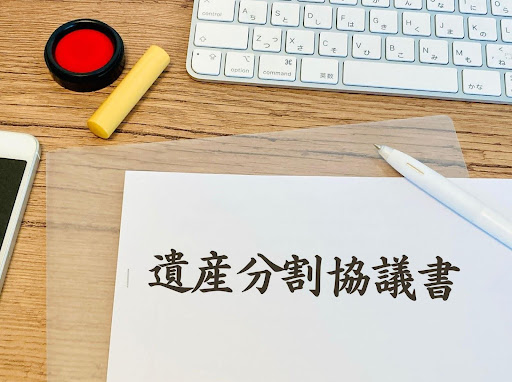
相続が発生した際、遺産をどのように分割するかを決めるためには、相続人全員の合意が必要です。その合意内容を正式な書類として残すのが「遺産分割協議書」です。
しかし、実際のところ、遺産分割協議書にはどのくらいの法的効力があって、どのように作成すればいいのかわからなくて、困っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺産分割協議書の具体的な作成方法、記載例、注意点までを詳しく解説します。遺産分割をスムーズに進めるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その結果を記録した書類のことをいいます。
相続が発生すると、遺産は一時的に相続人全員の共有財産となりますが、話し合いを経て正式に分割する必要があります。話し合いの結果を文書に残しておくことで、後々のトラブルを防ぎ、法的な証拠として活用することができます。
遺産分割協議書の法的効力
遺産分割協議書は、相続人全員の署名と押印があれば、法的な効力を持ちます。
この書類があることで、金融機関での預貯金の解約、不動産の名義変更、株式の移転手続きなどを行うこともできるでしょう。もし、遺産分割後の相続人の間で争いが生じた場合でも、協議書が有効であれば裁判所での証拠として認められます。
遺産分割協議書が必要になるケース
遺産分割協議書が必要となるのは、主に以下のようなケースで相続がある場合です。
- 遺言書がなく、法定相続分とは異なる遺産分割を行う
- 遺言書があるが、内容に不備があり遺言書が無効になった
- 遺言書があるが、内容に記載がない財産が発覚した
- 不動産や金融資産など、名義変更が必要な財産を相続する
- 相続人の間で将来的なトラブルを防ぐために文書化しておきたい
遺産分割協議書の作成方法
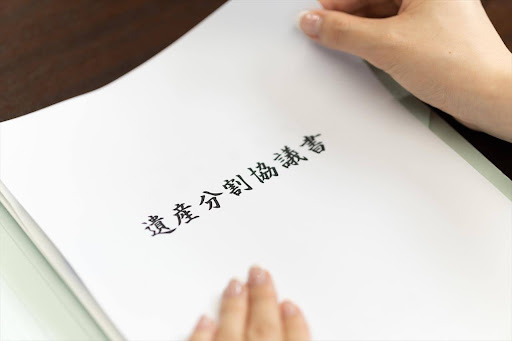
遺産分割協議書は正しい手順にて作成する必要があります。遺産分割協議の流れから具体的な記載内容や書き方を解説します。
遺産分割協議の流れ
遺産分割協議は、以下の流れで進めるのが一般的です。
- 相続人の確定:戸籍謄本などを取得して法定相続人を確認する
- 相続財産の調査:預貯金、不動産、株式、負債などを把握する
- 遺産分割協議:相続人全員で遺産の分け方について話し合う
- 協議内容の文書化:合意した内容を遺産分割協議書に記載する
- 各種手続き:協議書に基づき名義変更や相続税の申告などの手続き
遺産分割協議では、相続人全員の合意が不可欠です。意見が対立する場合には、公平な第三者を交えて話し合うことが望ましいでしょう。感情的にならず、冷静に協議を進めることが円滑な解決につながります。
協議内容の文書化では、合意した内容を明確に記載することが大切です。曖昧な表現を避け、相続人全員が納得できる内容にまとめることで、相続後のトラブルを防ぐことができます。署名と押印を忘れず、必要に応じて印鑑証明書を添付しましょう。
遺産分割協議書の記載例
遺産分割協議書には、決まったフォーマットはありません。以下の記載例を参考にポイントを抑えて作成しましょう。署名や押印が抜けていたり、曖昧な書き方をすると効力を失うので注意が必要です。
遺産分割協議書
被相続人〇〇(令和△年△月△日没)の遺産について、相続人全員の協議により、以下のとおり分割することを合意した。
1.相続人〇〇は、次の財産を取得する。
不動産 〇〇市〇〇町〇〇丁目◯番地の土地および建物
2.相続人〇〇と相続人△△は、次の財産を均等に分割して取得する。
預貯金 △△銀行△△支店(口座番号:123456789)
3.相続人▢▢は、次の財産を取得する。
株式 ▢▢株式会社100株
上記不動産は、長男〇〇が単独で相続する。預貯金は〇〇(長男)および、△△(長女)が均等に分割して相続する。株式は▢▢(次男)が単独で相続する。
・本協議書に記載のない遺産については、相続人全員の協議で別途決定する。
・本協議書に基づき、各種名義変更や手続きを速やかに行うものとする。
以上の内容に相違ないことを証明し、本書を作成し相続人全員が署名押印する。
令和✕年✕月✕日
〇〇(長男) 住所:東京都〇〇市〇〇町 印鑑
△△(長女) 住所:大阪府△△市△△町 印鑑
▢▢(次男) 住所:愛知県▢▢市▢▢町 印鑑
遺産分割協議書を作成する際の注意点
遺産分割協議書を作成する際には、正確な記載が求められます。記載内容に不備があると、法的に無効となったり、相続手続きが円滑に進まなかったりする可能性があるため、以下のポイントに注意して作成することが大切です。
- 被相続人の氏名と死亡日を記載
- 相続人全員が合意していることを示す内容を冒頭に記載
- 相続する財産の具体的な内容を記載
- 分割する配分がある場合は注釈を記載
- 相続人全員の名前と住所、押印
遺産分割を明確にするため、財産の内容を具体的に記載することが重要です。預貯金であれば銀行名や支店名、口座番号まで記載するようにしましょう。不動産であれば所在地など、登記簿情報を詳細に記載します。財産の特定が曖昧なままだと、手続きの際にトラブルが生じる可能性があります。
遺産分割協議書は、相続人全員の署名と押印がそろっていれば有効となります。押印は実印を使用するのが一般的です。また、法務局や金融機関での手続きをスムーズに進めるために、印鑑証明書の添付が推奨されています。署名や押印が一人でも欠けると、協議書が無効になってしまうため、必ず全員で確認しましょう。
遺産分割協議書の提出先と手続き

遺産分割協議書は、さまざまな手続きの場面で必要になります。
金融機関や法務局、税務署などへの提出が求められるケースが多く、それぞれ書類を準備しなければなりません。ここでは、主な提出先と手続きの流れを解説します。
税務署での手続き
遺産分割協議書は、税務署に相続税の申告をする際に提出が必要です。遺産分割の内容によっては、相続税の課税額に影響することがあります。
例えば、不動産を相続してそのまま所有する場合と売却して現金化する場合では、評価額が異なる可能性があり、課税額も変わってきます。また、相続人同士で特定の相続人に財産を多く譲る代わりに代償金を支払うケースでは、課税対象となる金額の計算方法が変わることもあるでしょう。
相続税の申告期限は、相続開始から10か月以内となるため、必要に応じて税理士のアドバイスを受けることをおすすめします。
金融機関での手続き
銀行や証券会社などの金融機関で、預貯金や株式を相続する場合は遺産分割協議書の提出が必要となります。ただし、金融機関ごとに必要な書類や手続きが異なる場合があるため、事前に金融機関に確認するようにしましょう。
法務局での手続き
不動産を相続する場合、法務局で名義変更(相続登記)を行います。この際、遺産分割協議書が必要となり、登記申請書とともに提出します。
相続登記の申請期限は2024年4月以降、相続開始から3年以内に義務化されました。遺産分割協議を行った場合は、協議の成立日から3年以内が期限です。
期限を過ぎると過料される可能性があるため、早めの手続きをするようにしましょう。また、登記申請には固定資産評価証明書や印鑑証明書などの書類が必要です。
相続でお困りの方は明石本町法律事務所にご相談ください
相続人同士の合意を得るのが難しい、書類の作成方法がわからない、手続きが煩雑で不安…そのようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。遺産分割協議書は、正確に作成しなければ法的に無効となる可能性もあります。
明石本町法律事務所では、相続手続きに精通した専門家が、遺産分割協議書の作成をはじめとした相続に関する幅広いサポートを提供しています。まずはお気軽にご相談ください。