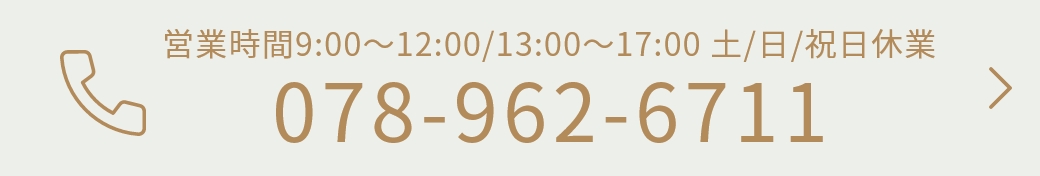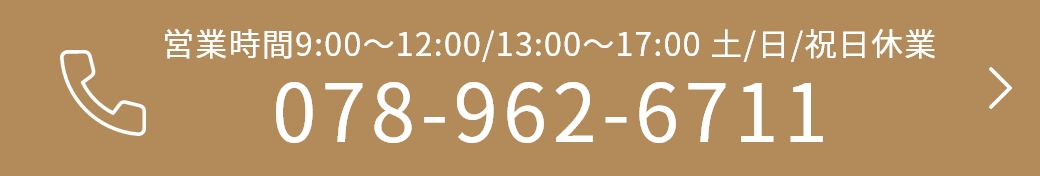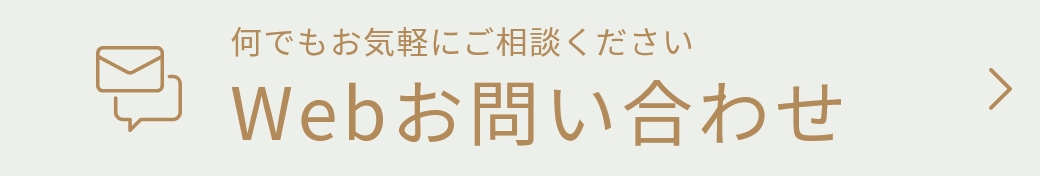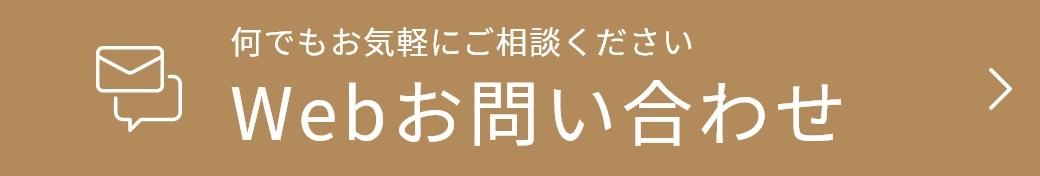遺言とは?遺言書の種類と作成方法、それぞれのメリットとデメリットを解説

遺言の作成は、遺産相続に自分の意志を伝える大切な方法ですが、具体的にどのような種類があり、それぞれのメリットとデメリットがわからない方も多いのではないでしょうか。相続人同士で争いの火種とならないためにも、適切な方法の遺言書を選びたいところです。
この記事では、遺言の種類と作成方法の選び方、それぞれの特徴を詳しく解説します。遺言書には、大きくわけて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、自分にあった方法を選ぶ参考にしてみてください。
遺言とは?
遺言とは、自分が亡くなった後の財産の分配方法や相続に関する意思を示すことをいいます。この意思を書面に残したものが遺言書といわれています。
遺言を残すことで、相続人同士の争いを防ぎ、自分の希望通りに財産を分配することができます。家族構成や財産の状況によっては、法定相続分と異なる分配を希望する場合もあるでしょう。特定の相続人に遺産を譲りたい場合にも、遺言は大きな役割を果たします。
例えば、亡くなる直前まで、献身的に介護をしてくれた長男の妻に遺産を相続したい場合にも役立ちます。本来は法定相続人でないため、相続することができませんが、遺言書に相続する内容を記載することで財産を譲ることができるでしょう。
また、日本の民法では、遺言書は法律で定められた方式に従って作成する必要があり、正しい手続きを踏まないと、遺言が無効になる可能性があります。
適切に作成された遺言書は、遺産相続をスムーズに進めるだけでなく、家族間のトラブルを未然に防ぐものとなってくれます。
遺言書の種類
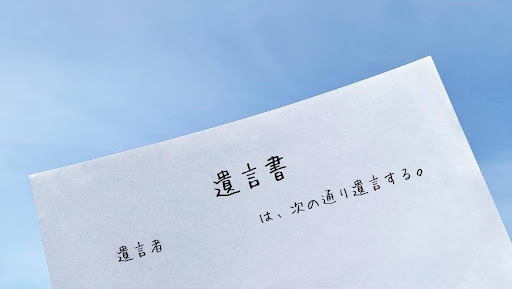
遺言書には大きく分けて3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれに特徴があり、作成方法や手続きが異なるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
例えば、誰にも見られずに自宅で手軽に作成したい場合は自筆証書遺言が合っているでしょう。相続の内容が複雑で、法的に確実性を求める場合は公正証書遺言が向いています。
遺産の評価額や相続する人数など、さまざまな要因を考えて、遺言書の種類を選ぶようにしましょう。
自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が自ら手書きで作成する遺言書のことです。公証人が不要で、自分の意思を自由に記載できます。ただし、法律で定められた形式を守らないと無効になるため、正しい書き方を理解することが大切です。
自筆証書遺言のメリット
- 自分で作成するので費用がかからない
- 証人が必要ないので遺言の内容を秘密にできる
- 好きなタイミングで書き直しができ内容も自由に決められる
自筆証書遺言のデメリット
- 民法の規定に従っていなければ無効になる恐れがある
- 紛失してしまったり、死後に相続人が遺言書を見つけられない恐れがある
- 遺言書の内容を書き換えられたり、隠されたりするリスクがある
遺言書保管制度の活用
2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が開始されました。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、家庭裁判所の検認が不要になるというメリットがあります。
費用は3,900円/1件で、保管までの流れは以下のようになります。
- 法務局で遺言書を提出し保管申請を行う
- 遺言者本人が法務局で本人確認を受ける
- 申請完了後、保管証を受け取る
家庭裁判所で行う検認
自筆証書遺言は、遺言書の保管者、もしくは遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所に提出して「検認」の手続きを行う必要があります。
検認とは、相続人に対して遺言の存在を知らせるもので、遺言書の形状、記載内容を明確にするために行います。遺言書が偽造や改ざんされることを防ぎ、相続人間でのトラブルを回避する目的があります。
相続トラブルの原因になりやすい
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、相続の内容がわかりにくかったり、法律に沿っていなかったりする場合、トラブルの原因となることがあります。相続人が多い場合や財産分配が複雑な場合には、特に争いを引き起こしやすいです。
例えば、「長男に自宅を相続させる」と記載した場合でも、具体的な物件の情報が明記されていないと、どの不動産を指しているのか解釈に相違が生まれ、争いになる可能性があります。「遺産を均等に分ける」といった曖昧な表現では、預貯金だけなのか不動産も含むのかなどの解釈が分かれてしまいトラブルの元になってしまいます。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言を有効にするためには、民法で定められた要件を満たす必要があります。これらの要件が守られていなければ、遺言は無効と判断されてしまうため、以下のポイントを抑えておきましょう。
- 遺言者が全文を自筆で記載する
- 日付を明記する
- 署名と押印をする
- 修正する際は、正しい訂正方法を守る
関連コラム:遺言書(自筆証書遺言)を自分で作成する方法|無効にならないための書き方
公正証書遺言とは
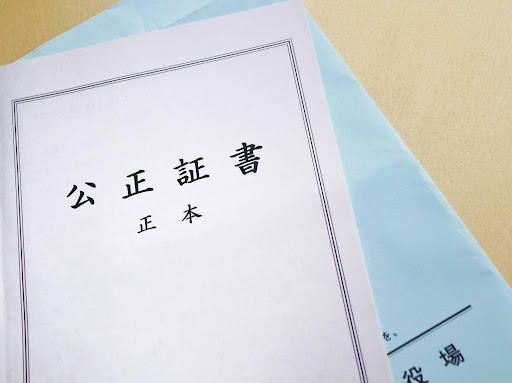
公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言書のことをいいます。公証人が作成するため、法的に確実で無効になるリスクが少ない遺言書です。証人が必要で、作成には費用がかかりますが、家庭裁判所の検認が不要となるメリットがあります。
公正証書遺言のメリット
- 公証人が関与するため形式不備がなく、遺言が無効になることは少ない
- 家庭裁判所の検認が不要なので相続開始後スムーズに手続きが進む
- 公証役場で保管されるため紛失や改ざんの心配がない
公正証書遺言のデメリット
- 公証人手数料や証人2名の謝礼など費用が発生する
- 遺言の内容を証人に知られる可能性がある
公正証書遺言の費用相場
公正証書遺言の作成には、公証人手数料が必要となります。財産の額によって手数料が変動するため、詳細な金額は事前に確認しておくことが重要です。一般的には、5〜10万円程度の費用が必要になります。
関連コラム:遺言書作成にかかる費用はいくら?遺言書の種類と依頼する専門家別に解説
公正証書遺言の証人の選び方
公正証書遺言には2名の証人が必要です。ただし、相続人や未成年者は証人になれないなど、一定の条件があります。以下の人は証人に慣れないため注意してください。
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者
- 推定相続人の配偶者や直系血族
- 受遺者の配偶者や直系血族
もし、証人が見つけられない場合は、公証役場で1人当たり6,000円前後で紹介してもらうこともできます。遺言書作成を弁護士などに依頼している際は、証人も担うのが一般的です。
公正証書遺言でも無効になるケースはある?
公正証書遺言で遺言が無効になるケースは極めて稀ですが、以下のような理由で無効になってしまうことはあります。
- 認知症などで遺言者の意思能力が欠いていた
- 証人が未成年などで不適格者だった場合
- 遺言者の思い違いや勘違いによって遺言内容を記載した場合
秘密証書遺言とは
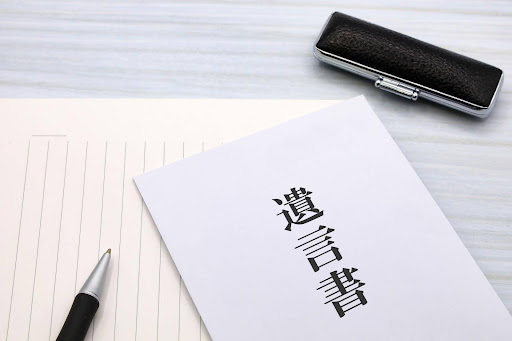
秘密証書遺言は、遺言の内容を自分で作成して、遺言書が存在することのみを公証人と証人に証明してもらう遺言書のことです。公正証書遺言のような公的な証明がなく、開封後に内容の不備が判明する可能性があります。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言者以外が内容を知ることはないので秘密にできる
- 改ざんされるリスクが低い
秘密証書遺言のデメリット
- 家庭裁判所での検認が必要
- 内容自体は公証人が確認しないため形式に不備の可能性がある
自分に合った遺言書がわからないときはご相談を
遺言書は自分の財産を希望通りに分配して、相続トラブルを防ぐために大切なものです。しかし、多くの方はどの形式が自分に合っているのか、また法的な効力があるように正しく書けるのかと不安を感じてしまうものでしょう。作成方法だけでなく遺言内容もどのようにするかもスムーズな相続には欠かせません。
明石本町法律事務所では、弁護士が法的に有効な遺言書の作成をサポートし、相続人の意向を整理しながら最適な内容をご提案します。公正証書遺言や遺言執行者の指定なども対応可能ですので、お気軽にご相談ください。