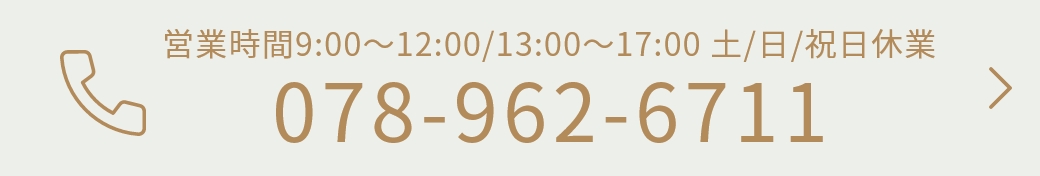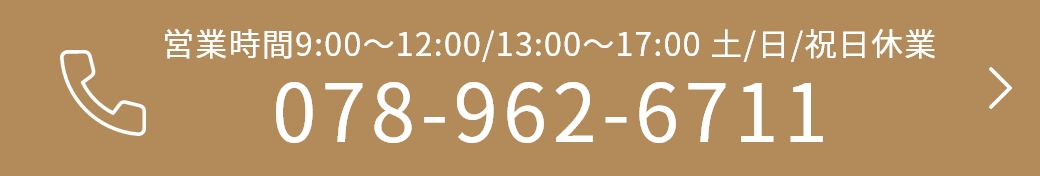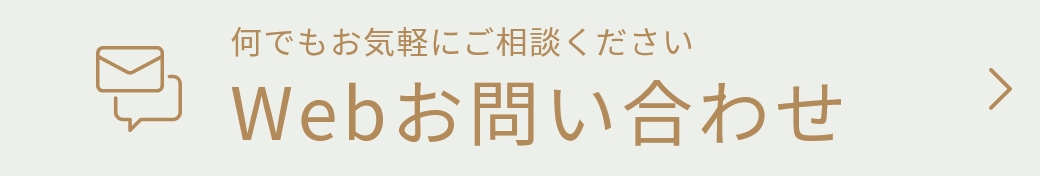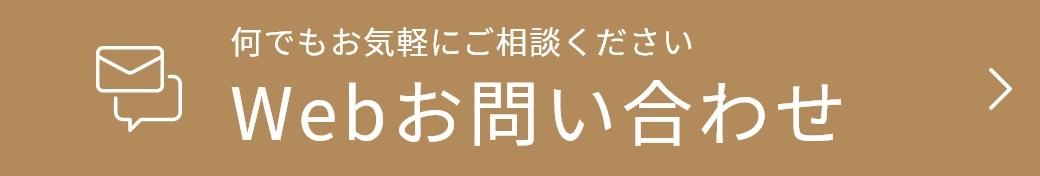遺言書(自筆証書遺言)を自分で作成する方法|無効にならないための書き方
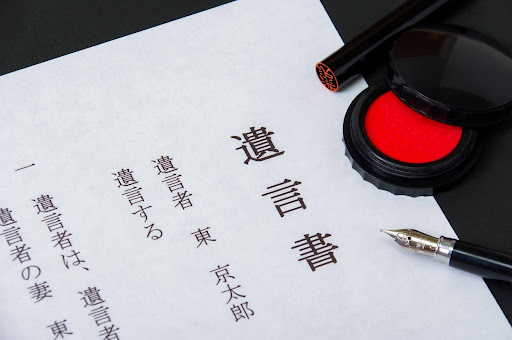
自筆証書遺言は、自分で作成できる遺言書ですが、具体的な書き方がわからない方も多いのではないでしょうか。誤った書き方をすると無効になったり、意図した通りに財産が分配されなかったりするのは避けたいところです。
また自筆証書遺言は、自分で手軽に作成できる一方で、法律の要件を満たさなければ無効になるリスクもあります。この記事では、自筆証書遺言の基本から、書き方のポイント、無効を防ぐための注意点を解説します。
自分で作成できる遺言書

自分で作成できる遺言書として、「自筆証書遺言」があります。公証役場を利用せずに、自宅で自由に書くことができるため費用を抑えられる点が魅力です。ここでは、自筆証書遺言の基本情報やメリット・デメリットを解説します。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が自ら手書きで作成する遺言書のことです。公証人が不要で、自分の意思を自由に記載できます。ただし、法律で定められた形式を守らないと無効になるため、正しい書き方を理解することが大切です。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言には以下のようなメリットがあります。
- 自分で作成するので費用がかからない
- 証人が必要ないので遺言の内容を秘密にできる
- 好きなタイミングで書き直しができ内容も自由に決められる
自筆証書遺言のデメリット
一方でデメリットとして以下があげられます。
- 民法の規定に従っていなければ無効になる恐れがある
- 紛失してしまったり、死後に相続人が遺言書を見つけられない恐れがある
- 遺言書の内容を書き換えられたり、隠されたりするリスクがある
自筆証書遺言は法務局で保管
2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が開始されました。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、家庭裁判所の検認が不要になるというメリットがあります。
費用は3,900円/1件で、保管までの流れは以下のようになります。
- 法務局で遺言書を提出し保管申請を行う
- 遺言者本人が法務局で本人確認を受ける
- 申請完了後、保管証を受け取る
自筆証書遺言の見本
自筆証書遺言には、民法で定められた要件があります。法律上の効力を発揮させるために必要なもので、要件に準じて作成しなければなりません。以下の見本を参考にしてみてください。
遺言書
遺言者 明石太郎は本遺言書により、以下の通り遺言する。
1 私は、私の所有する別紙1の不動産を、長男の明石一郎(昭和◯年◯月◯日生)
に相続させる。
2 私は、私の所有する別紙2の預貯金を、次の者に遺贈する。
住 所 〇〇県〇〇市〇〇町◯丁目◯番地
氏 名 神戸花子
生年月日 昭和◯年◯月◯日
3 私は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住 所 〇〇県〇〇市〇〇町◯丁目◯番地
職 業 弁護士
氏 名 姫路一夫
生年月日 昭和◯年◯月◯日
令和◯年◯月◯日
住所 〇〇県〇〇市〇〇町◯丁目◯番地
明石 太郎 印
(参考:遺言書の様式等についての注意事項|法務局)
自筆証書遺言の民法で定められた要件
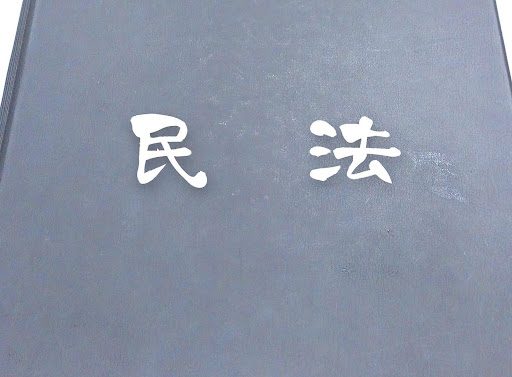
自筆証書遺言を有効にするためには、民法で定められた要件を満たす必要があります。これらの要件が守られていなければ、遺言は無効と判断されてしまいます。ここでは、自筆証書遺言を作成する際に守るべき法的要件を解説します。
全文を自筆で書く
遺言者は、すべて手書きでの記載が必要です。パソコンや代筆による遺言書は認められていません。ただし、財産目録のみは、パソコンを使ったり通帳を印刷したものでも認められています。
作成した日を明記
遺言書の見本のように「令和◯年◯月◯日」と具体的に記載する必要があります。
一般的な文書でよく使われている「◯月吉日」などの表記にしてしまうと無効になるため注意が必要です。年度の記載漏れも無効の原因になるため忘れないようにしましょう。
訂正ルールを遵守
遺言書の文章には訂正する際のルールが定められています。
- 訂正箇所に二重線を引く
- 訂正印を押す(認印でも可)
- 欄外に訂正した旨を記載
訂正する際はこれらを守らなければなりません。訂正は、変更や追加等がある場合に行いますが、基本的には、はじめから書き直すことが推奨されています。
署名と押印
遺言者は署名をして押印(実印・認印でも可)を行います。署名は必ず自筆でするようにしましょう。また、陰影がぼやけてにじんだり、消えたりしている場合は無効になる恐れがありますので、しっかりと押印することが大切です。
自筆証書遺言の書き方のポイント

自筆証書遺言を作成する際には、財産の把握や相続内容を明確にしておくことが大切です。遺言書の作成前にしっかり準備を行うことで、相続人が遺産を円滑に受け取ることができ、不要な対立も避けられるでしょう。
相続する財産を把握する
遺言書を作成するときには、自分が所有している財産を整理しましょう。一般的には、以下のようなものが相続財産としてあげられます。
- 不動産の登記簿(全部事項証明書)
- 預貯金の通帳、取引証明書
- 証券会社やFX会社、仮想通貨交換所の取引資料
- ゴルフ会員権の証書
- 生命保険証書
- 自動車、絵画や骨董品などの動産の明細書
- 借入金や債務の明細書
- 買掛金や未払い手形など
- 固定資産税など未払いの税金や費用
財産目録を作成する
相続する財産が把握できれば、財産目録の作成をしておきましょう。 財産目録は、相続財産の一覧表であり、資産と負債を整理して相続人が把握しやすくするために作成されます。
法務局の遺言書保管制度を利用する場合、財産目録はパソコンで作成し印刷したものを添付することも可能です。
誰に何を相続させるのか明確にする
「〇〇の土地を長男に」「預貯金のうち〇〇万円を次男に」といったように、具体的な財産の分け方を明記しましょう。誰に何を相続させるのかが不明確な表現になってしまうと、相続人同士で解釈の相違が生まれ、後々の相続トラブルの原因になってしまいます。
遺言執行者を指定する
遺言執行者を指定することで、遺言の内容を適法に執行できます。ただし、遺産分割協議を取り仕切る権限はありません。弁護士や信頼できる相続人を指定することで、円滑に相続手続きが可能になります。
遺言書を自分で作成する際の注意点
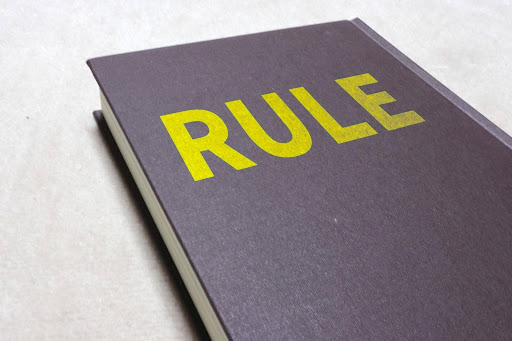
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、法的に無効となるケースも少なくありません。適切なルールを守り、確実な遺言書を作成するために注意点を押さえておきましょう。
遺言書が無効になりやすいケース
自筆証書遺言が無効になりやすいケースとして以下があげられます。
- 記載内容に不備がある
- 遺言者の意思能力が疑われる状況で作成された
- 遺言書の内容が法律に反している
- 夫婦共同の遺言と記載してしまっている
遺言書の保管方法
自宅で保管する場合は、相続人が見つけられる場所に保管して、信頼できる人に伝えておくことが大切です。紛失や改ざんのリスクをできるだけ減らしたいのであれば、法務局の遺言書保管制度を利用するのも有効な手段です。
遺言書で決められること
遺言書で決められることには限りがあります。間違って遺言書で決められないことも記載しないように、以下の内容を確認しましょう。
- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定
- 相続人以外の受遺者への遺贈
- 遺言執行者の指定
- 相続人の廃除
など
遺言書を自分で作成する場合でも気軽にご相談ください
自筆証書遺言は、自分で手軽に作成できる反面、法律の要件を満たしていないと無効になるリスクがあります。正しい書き方を理解し、法務局の保管制度などを活用するなどして、確実に相続人に渡るようにしましょう。
明石本町法律事務所では、弁護士が法的に有効な遺言書の作成をサポートし、遺言者の意向を整理しながら最適な内容をご提案します。自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言や遺言執行者の指定なども対応可能ですので、お気軽にご相談ください。