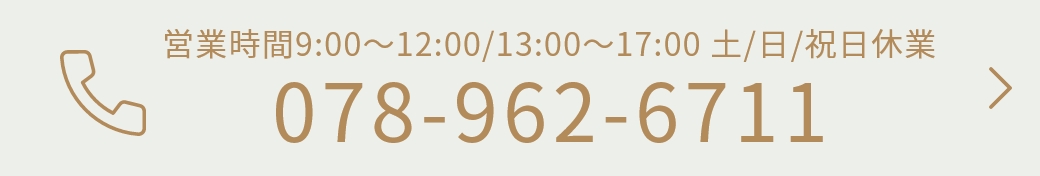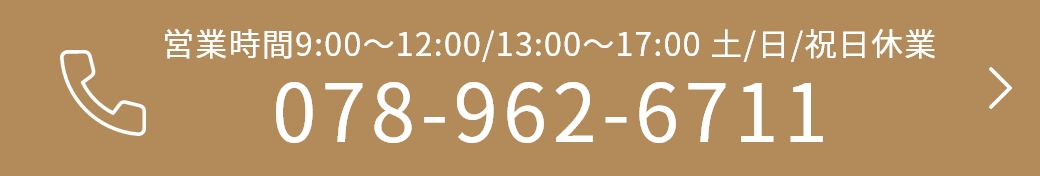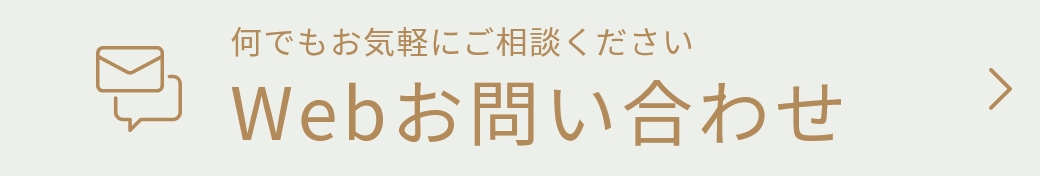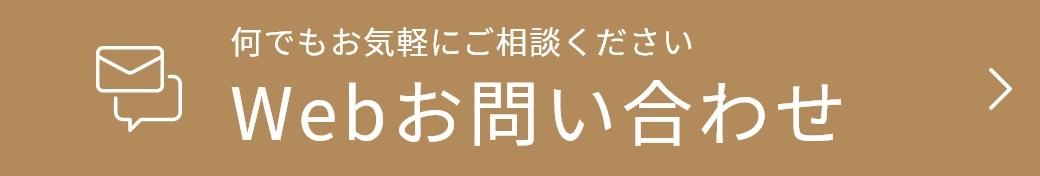遺産分割調停とは?大まかな流れと有利に進めるためのポイントを解説

遺産分割の話し合いがまとまらず、相続人同士で対立が起こることは少なくありません。特定の相続人が応じなかったり、遺産を相続する割合で合意が得られなかったりと、円滑に進まなくなってしまうことがあります。
遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が中立な立場で話し合いを仲介し、公平な分割を目指すもので、訴訟よりも負担が少なく協議することが可能です。
この記事では、調停の流れや有利に進めるためのポイントを解説します。
遺産分割調停とは?

遺産分割調停とは、相続人間で遺産の分け方について話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所を通じて行う話し合いの手続きのことをいいます。
裁判官と調停委員が中立の立場で相続人全員の意見を聞き、解決案を提示したり助言を行ったりしながら合意形成を目指すものです。一般的には、相続人同士の遺産分割協議で合意が得られなかった場合に行われます。
調停委員とは?
調停委員とは、家庭裁判所で行われる調停の手続きにおいて、中立的な立場から当事者間の話し合いを仲介する者のことをいい、具体的には、原則として40歳以上70歳未満の人で、弁護士・医師・大学教授・公認会計士・不動産鑑定士・建築士などの専門家のほか、地域社会に密着して幅広く活動してきた人などが選ばれます。
調停委員会は裁判官と調停委員2人以上で構成されており、遺産分割の調停においては、男女1人ずつが選任されます。
調停が必要になるケース
遺産分割調停は、以下のようなケースで行われることがあります。
- 相続人同士で話し合いがまとまらない
- 一部の相続人が遺産分割に応じない
- 遺産の評価額や分割方法について意見が対立している
- 遺言書の内容に疑義がある
相続人同士の感情的な対立があって話し合いが進まない場合など、遺産分割協議では解決できないことがあります。このような場合に、遺産分割調停を行うことが一般的です。
遺産分割調停を申し立てができる人
遺産分割調停の申し立てができるのは、法定相続人と受遺者となります。受遺者とは、遺言書の内容によって財産を譲り受ける者のことをいい、例えば、孫や愛人などが該当することがあります。
遺産分割調停のメリットとデメリット
遺産分割調停にはメリットとデメリットが伴います。遺産分割調停を申し立てる前に確認しておきましょう。
| 遺産分割調停を行うメリット | 遺産分割調停を行うデメリット |
|---|---|
|
|
遺産分割調停のメリット
遺産分割調停を行うメリットとして以下があげられます。
- 公平な解決が期待できる
- 訴訟よりも負担が少ない
- 非公開で進めることができる
- 相続人同士の関係が維持しやすい
遺産分割調停を利用するメリットは、公平な解決が期待できる点です。家庭裁判所の調停委員が中立的な立場で関与し、相続人それぞれの意見を尊重しながら分割方法を提案するため、一方的に不利な条件を押し付けられる心配が少ないです。訴訟よりも手続きが簡単で、費用や時間の負担を抑えられるのもメリットのひとつでしょう。
遺産分割調停は相続人同士の冷静な話し合いを促す場となるため、相続人どうしの関係維持につながりやすいのもメリットです。
遺産分割調停のデメリット
一方で、遺産分割調停には以下のデメリットがあげられます。
- 時間がかかる場合がある
- 強い強制力がない
- 自分の主張が通るとは限らない
- 相続人全員の協力がないと難航する
話し合いが長引くと、調停の成立までに時間がかかってしまう場合があります。相続人同士の意見が大きく対立していると、2年近くかかることも少なくありません。
また、調停には裁判のような強制力がないため、相続人の合意が得られなければ不成立に終わることもあります。相続人全員が調停に協力する必要があり、一部の相続人が協力しない場合や出席しない人がいると話し合いが難航してしまうこともあるでしょう。
遺産分割調停の大まかな流れ

遺産分割調停の大まかな流れを解説します。
1.必要書類の準備
遺産分割調停を申し立てるのに必要な書類、相続財産に関わる資料の準備を行います。代襲相続が発生していたり、相続人に直系尊属がいたりする場合は追加で必要となる資料がありますので、詳しくは、裁判所が公開している内容を参照ください。
申し立てに必要な書類
- 遺産分割調停申立書
- 相続人全員の住民票または戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 遺産に関する証明書
相続財産に関する資料
- 預貯金の残高証明書
- 不動産の登記簿謄本
- 株式や有価証券の資料
- 借金がある場合の負債証明書
- 財産の評価額を示す資料(不動産査定書など)
(引用:遺産分割調停書|裁判所)
2.家庭裁判所に申し立てる
相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書と必要書類を提出します。
3.家庭裁判所から調停日通知の連絡
家庭裁判所から調停期日が指定された通知書が送付されます。遺産分割調停の申し立てをしてから、2週間から1ヵ月前後を目安にするとよいでしょう。
4.調停期日に家庭裁判所で調停を行う
遺産分割調停が行われる日は、調停手続の内容について各相続人は、説明を受けることになります。その後、調停委員が順番に相続人を調停室へ呼び、個別に意見や主張を聞きながら論点を整理していきます。
調停は、基本的に調停委員2名(基本的には男女各1人)が進行し、裁判官が直接関与することは少ないです。調停室では、本人確認を経て30分程度の話し合いが行われ、事前に提出した事情説明書や答弁書をもとに質問を受けることが一般的です。
この話し合いは申立人と相手側それぞれで行われ、相続人同士が直接対面することはありません。最後に調停委員がその日の内容を総括し、合意できた点や次回に持ち越す課題、次回の調停期日と準備すべきことを確認して終了となります。
5.調停が成立するまでは1〜2年程度
遺産分割調停においては、1日の調停で終わることはほとんどありません。話し合いの続きは、次回の期日で行われます。基本的には約1ヵ月後となります。
当事者間で合意ができれば調停は成立となりますが、一般的には複数回繰り返すことになります。調停手続が完了するまでに、1〜2年の期間がかかることを想定しておきましょう。
6.合意された場合は調停書の作成
遺産分割調停の結果、相続人全員が合意に至った場合は、家庭裁判所が調停証書を作成します。調停証書は遺産分割協議書と同じ効力をもつため、預貯金の名義変更や相続登記などで使用することが可能です。
(関連コラム:遺産分割協議書とは?具体的な作成方法と記載例を解説)
7.調停が不成立の場合は遺産分割審判
遺産分割調停でも話し合いがまとまらず、合意に至らなかった場合は、当事者が希望すれば遺産分割審判へ移行します。裁判官が相続人の主張や書類にもとづいて、遺産分割の判断を行います。
遺産分割調停を有利に進めるためのポイント

遺産分割調停を有利に進めるには、事前の準備と冷静な対応が必要です。ここでは、調停の進め方のポイントを解説します。
自分の主張を整理しておく
遺産分割において自分の主張を明確にして、証拠を準備しておくことが大切です。預貯金の残高証明書や不動産の登記簿謄本など資料をそろえておくとよいでしょう。
また、自分の主張をあらかじめ書面にまとめておくのも効果的です。何も準備していない状態だと、調停委員の質問にも感情的に応えてしまい心象を悪くしてしまうこともあります。
冷静に落ち着いて回答するためにも、自分の主張は整理しておきましょう。
必要に応じて弁護士に相談する
弁護士から専門的なアドバイスを受けることで、交渉を有利に進めることができます。
調停委員とのやり取りでは、法律にもとづいた主張を行い、その主張に合理性があるのかが有利に進めるためのポイントです。遺産が多額である場合や相続人同士の対立が激しい場合は、専門家のサポートを受けることも検討してみましょう。
遺産分割調停でお困りの方は明石本町法律事務所にご相談を
遺産分割調停は、法的な根拠にもとづいて主張することが大切です。しかし、ほとんどの方は、その主張が法的に合理的なのか判断するのは難しいものです。
明石本町法律事務所では、相続問題に精通した専門家が、遺産分割調停をはじめとした相続に関する幅広い支援を行っています。不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください